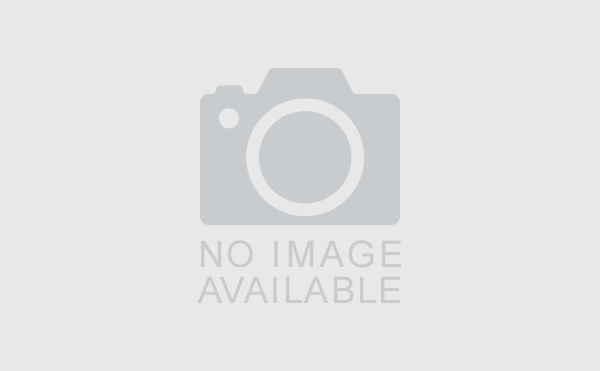「サステナビリティ(気候・自然関連)情報開示を活用した経営戦略立案のススメ」が公表されました
令和7年4月21日、環境省より、改訂された「サステナビリティ(気候・自然関連)情報開示を活用した経営戦略立案のススメ~TCFDシナリオ分析と自然関連のリスク・機会を経営に織り込むための分析実践ガイド~」が公表されました。以下、背景と概要はニュース・リリースからの引用です。
背景
脱炭素社会実現に向けた気候関連のリスク・機会の情報開示に加え、自然再興(ネイチャーポジティブ)の実現に向けた自然関連の依存・影響及びリスク・機会に関する情報開示が国内外で進展しています。
気候変動対策と生物多様性保全はトレードオフが生じることも考えられる一方、相互関係(ネクサス)を理解し自然再興と統合的に気候変動対策に取り組むことでコベネフィットを生み出す可能性も考えられます。資源の調達・活用のあり方と関わりが深いネイチャーポジティブと、資源の一つであるエネルギーの活用のあり方にも深く関わるカーボンニュートラルは、相互に関係するものであり、企業目線からすれば統合的に取り組むべきものです。
概要
令和6年度、環境省で実施した企業の脱炭素化実現に向けた統合的な情報開示に関する促進事業において、気候関連財務情報開示を活かした自然関連財務情報開示モデル支援(ネイチャー開示実践事業)を実施しました。自然資本に関する情報開示について今後さらに企業の対応が求められていくことが想定されるため、自然資本に関する「シナリオ分析」と「目標設定」について伴走支援しました。
今般、その結果を踏まえ、昨年度取りまとめたガイドに、自然関連情報開示の高度化に向けたシナリオ分析と目標設定の策定プロセスについて追加する等の、改訂を行いました。
補足
一般的に、「TCFDシナリオ分析」への対応は投資家に向けた情報開示の意味合いも強く、未上場企業においては敷居が高いところでもあります。
一方で、サプライチェーンや政策からの後押しもあり、気候変動対策としてカーボンニュートラルを取組の中心とする流れがあります。カーボンニュートラルは、気候変動対策において「緩和策」と言います。
ここで、企業経営の視点で気候変動対策を考える際にカーボンニュートラル以上のことにも目を向けると、TCFDシナリオ分析が大きな意味を持って来ます。
誤解を恐れずに述べると、カーボンプライシングが制度化されていない現状(※)、大気へのCO2排出に法規制のないこともあり、国内においてカーボンニュートラルに取り組むべき義務や根拠は強くありません。
むしろ、異常気象による直接・間接的な被災、あるいは気候が変わりつつあることによる自然からの恵みの減少などの影響が大きいことを認識する必要があります。この影響に対応することを「適応策」と言い、BCP(Business Continuity Plan:業継続計画)策定に含まれます(下図参照)。
この適応策を検討するにあたり、企業経営のリスク(と機会)の認識・理解の助けとなるのが「TCFDシナリオ分析」の手法です。この場合、投資家に向けた情報開示が目的ではないので、自分たちが必要とする部分だけを切り取って「TCFDシナリオ分析」を利用することも可能です。BCPを策定する際には「TCFDシナリオ分析」の手法が参考になると言うことです。
(※)2026年度の排出量取引制度から国内でも順次導入されていきます

公開資料
サステナビリティ(気候・自然関連)情報開示を活用した経営戦略立案のススメ~TCFDシナリオ分析と⾃然関連のリスク・機会を経営に織り込むための分析実践ガイドVer2.0~
- 【本編】
- 【別添】(シナリオ分析:株式会社竹中工務店、KDDI株式会社 目標設定:TOPPANホールディングス株式会社)
関連情報
以上(2025/4/24)